なぜ鍼灸に心理学が必要なのか
鍼灸カウンセリング協会 会長 中川 晶 先生
 奈良医科大学卒. 大阪赤十字病院で内科研修を終えた後、大阪大学精神医学教室に入局し神経症・うつ病・心身症の臨床研修を重ねてから大阪大学病院神経科・精神科で心身症の外来を続ける。同時に近畿大学東洋医学研究所にて漢方治療を学び心身症の治療に精進。現在は心療内科の専門医として心身症などの治療に当たっている。(現職)なかがわ中之島クリニック院長、奈良学園大学教授、日本保健医療行動科学会会長
奈良医科大学卒. 大阪赤十字病院で内科研修を終えた後、大阪大学精神医学教室に入局し神経症・うつ病・心身症の臨床研修を重ねてから大阪大学病院神経科・精神科で心身症の外来を続ける。同時に近畿大学東洋医学研究所にて漢方治療を学び心身症の治療に精進。現在は心療内科の専門医として心身症などの治療に当たっている。(現職)なかがわ中之島クリニック院長、奈良学園大学教授、日本保健医療行動科学会会長まずは、「なぜ 鍼灸師に心理学が必要か…」について述べたいと思います。
元々我が国では心身一如という考え方があって古くから鍼灸師はココロとカラダを同時に診てきました。
しかし、近代に入ってからはカラダを機械として考える見方が一般化してきました。そのおかげで診断や治療は精密になったのですが、ココロの治療からは遠ざかっていきました。
現代医学でも同様です。
最近ではココロを無視した医療はいま曲がり角にきています。その反省からか時代はココロの専門家を求めるようになりました。それが臨床心理士なのかもしれません。
しかしココロが無視されているからといって、ココロの専門家の養成をするというのはあまりに安易な方法です。何故ならココロとカラダは一体のもので切り離して治療するというのは無理があります。
日本人はココロの問題をカラダを通して表現するという複雑なやり方をしがちです。
日本ではココロの病気は恥ずかしいものとされている風潮があるので、素直にココロのトラブルを表現出来ません。
その結果、肩こり・腰痛・頭痛などの身体症状としてココロのトラブルが出てくることが多いのです。
身体症状は臨床心理士では分かりません。
鍼灸にくる患者さんの多くがストレスを訴えるのは身体的な治療を通して心理治療をして欲しいという現れです。
しかし、現在の鍼灸教育ではココロに関する科目はきちんと教えられているところは非常に少ないのが現状です。
そこで、きちんとした形でココロに関する勉強(精神医学・臨床心理学・心身医学など)をしていただいて日々の診療に役立てて頂こうという趣旨で「鍼灸心理師」資格を作りました。
さて、「鍼灸心理師」の基本的な考え方というのは「治療」よりむしろ「癒し」を大事にしていこうという立場です。
それでは「癒し」とは何かということについて少し考えてみました。以下の文章は「現代福祉科学事典」という書物に筆者が「癒し」の項目として書いたものです。
現代医学において「癒し」という用語が用いられることは希です。専ら「治療」という言葉が使われます。治療と癒しの違いは何かというと働きかける対象が異なるということです。すなわち「治療」の対象が客観的な生物学的過程である「疾病」(Disease)であるのに対して「癒し」の対象は主観的な心理、社会的過程である「病い」(Illness)やもっと広い意味に取れば「患い」(Suffering)ということになります。
「癒し」で重要なのは相手の主観的な部分に働きかけるということです。「癒し」の基本のひとつは相手の「こわばり」「こだわり」を解いて、安心できる状態に回帰させていくことであります。「こだわり」「こわばり」というのはとりも直さず主観なのです。
「癒し」という言葉は宗教的な響きを含み、原義としての対象は医療問題に限定されるものではありませんが、近年医療人類学においては「疾病」(Disease)と「病い(Illness)が区別され、「病い」に対応する言葉として「癒し」(Healing)が定義されています。
「癒し」は治療者が施すという一方通行の関係ではなく、患者と治療者が協力して作り上げていくものであります。ここで重要なのは患者と治療者が共有する価値体系あるいは信条体系です。
つまり患者の主観の中で苦悩が軽減されるためには、どのようなことをするのが価値をもつのか、あるいはどのような信条が苦悩の軽減に役に立つのかを治療者・患者の双方参加で考えて実践することです。
「癒し」という実践のなかで留意すべきことは治療者側の構えであります。ともすれば治療者は自分の知識の枠内に患者を導こうとするあまり患者に対する聞き方がクローズド・クエッション(答えが「はい」か「いいえ」となる問い方)になりがちですが、「癒し」は双方参加が原則であります。オープンド・クエッション(答えが「はい」「いいえ」ではなく考えを述べねばならない問い方)を心掛ける必要があります。
現代医学は生物科学を基礎において著しい発展をとげ、その応用として医療を位置づけてきました。確かに急性疾患や外傷に対して現代医学はその有効性、卓越性は疑うべくもありません。しかし、慢性疾患・神経症・心身症といった病気に対しては突如切れ味が悪くなります。
何故かというと、これらの疾患では主観が病気に深く関わっていて、客観的であることを旨とする生物科学は立ち往生してしまうからであります。主観的なものを客観的な方法で扱うことには無理が生じます。結局、病気の客観化できる部分にだけ焦点を当てた治療が行われることになり、その他の部分は切り捨てられることになります。
エンゲル( Engel,George)は現代医学の生物科学万能主義を批判して「プロクルテスのベッド」を引用しています。プロクルテスというのはギリシャ神話に出てくる盗賊で、旅人を捕まえては用意したベッドにくくりつけるのですが、旅人の足がベッドより長ければ切り落とし、短ければ引き延ばしてベッドと同じ長さにそろえて楽しんだといいます。
生物科学万能主義からは「癒し」という発想は出てくることはありません。
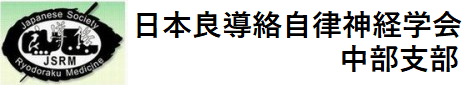
 Menu
Menu